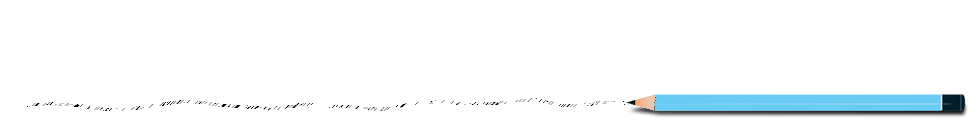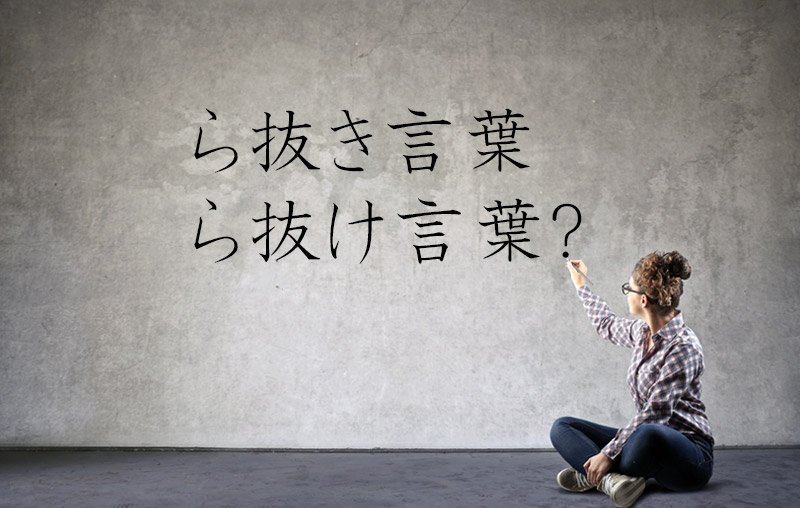「見られる」を「見れる」、「食べられる」を「食べれる」、「来られる」を「来れる」。このように、動詞に可能の意味を持たせる際に、助動詞「られる」から「ら」を抜いて用いる言葉を「ら抜き言葉」と呼びます。この「ら抜き言葉」は、しばしば日本語の乱れの代表例として取り上げられてきました。
しかし、一方でこの現象を単なる日本語の乱れとするのではなく、言葉の自然な変化や合理化の一環と捉える見方も存在します。
この記事では、「ら抜き言葉」がなぜ生まれ、どのように使われ、そして社会的にどう受け止められているのかについて考察していきます。
なぜ「ら抜き言葉」が使われるようになったのか
「ら抜き言葉」が使われるようになった背景には、いくつかの理由が考えられます。
一つは、助動詞「られる」が持つ意味の多さです。「られる」という言葉には、以下の4つの意味があります。
- 可能: 「この茸は食べられる」
- 受身: 「先生に褒められる」
- 尊敬: 「社長が来られる」
- 自発: 「この詩からは悲しみが感じられる」
「られる」には、このように多くの意味があるため、文脈によっては少しわかりにくくなることがあります。
そこで、「食べれる」「見れる」のように「ら」を省略することで、可能の意味であることを明確化したいという心理が働いたのではないかと考えられます。この場合の「ら抜き」は、可能の意味に限定して解釈されるという大きな利点があります。
また、言葉がよりシンプルで使いやすい形に変化していく自然な流れの一部という見方もあります。「書く」が「書ける」、「読む」が「読める」というように、他の多くの動詞では「~エる」という形で可能の意味を表します。これに倣って、「食べられる」よりも「食べれる」、「見られる」よりも「見れる」のほうが、元の形より短くて言いやすい、と感じる人が増えたのかもしれません。
「ら抜き言葉」ではなく「ら抜け言葉」?
この「ら抜き言葉」について、人々の意見はさまざまです。
「ら抜き言葉」を肯定的に捉える人たちの中には、これは言葉の自然な変化であり、「ら抜き言葉」ではなく「ら抜け言葉」と呼ぶべき、という意見があります。「抜いた」のではなく、自然に「抜け落ちた」というニュアンスです。意味がわかりやすくなるというメリットを重視し、話し言葉ではもう普通に使われているのだから、問題ないのではないか、という立場です。
一方で、昔からの正しい日本語の形を大切にしたいと考える人たちからは、「ら抜き言葉」は伝統的な文法から外れており、日本語の乱れだと感じるという声が根強くあります。特に、きちんとした言葉遣いを心がけている人にとっては、違和感や不快感を覚えることもあるようです。
「ら抜き言葉」の現代社会での使われ方
「ら抜き言葉」が今の社会でどのくらい受け入れられているかは、少し複雑な状況です。
文化庁が定期的に行っている「国語に関する世論調査」を見ると、「ら抜き言葉」を使う人の割合は、特に若い世代で高くなっている傾向があります。つまり、時代とともに徐々にその浸透度を増しているということです。
とはいえ、新聞やテレビのニュース、雑誌などのメディアでは、現在でも「ら抜き言葉」は基本的に使われません。アナウンサーが話す言葉はもちろん、インタビューなどで一般の人が「ら抜き言葉」を使ったとしても、字幕や記事では「ら」を入れた形に校正されていることがほとんどです。これは、メディアが多くの人に向けて情報を発信する上で、言葉の規範を意識し、誤解や不快感を与えないように配慮しているためです。
このように、普段の会話ではよく耳にする「ら抜き言葉」も、改まった場面や書き言葉では、まだ「正しい日本語」とは言い切れない状況にあるといえます。
「ら抜き言葉」をどう使うべきか
「ら抜き言葉」は、時と場合、相手など、状況に応じて使い分ける柔軟さが大切です。
作文、レポート、仕事のメールなど、きちんとした文章を書く時
この場合は、「ら」を入れた伝統的な形(例:「見られる」「食べられる」)を使いましょう。正確な文章を書くことが求められる状況であるということ以外に、相手に与える印象という点でもプラスになります。
友達との普段の会話やSNSなど、くだけた場面で話す時
親しい間柄であれば、「ら抜き言葉」を使っても問題ないです。相手も普段から使っているかもしれませんが、相手の言葉遣いを指摘するような無粋なことはやめておきましょう。
小説や漫画、脚本などのセリフ
登場人物の年齢や性格、話し方をリアルに表現するために、会話文であえて口語感の強い「ら抜き言葉」を使う手法はよく見られます。逆に、真面目なキャラクターを演出する際に、「ら抜き言葉」を使わないというのも非常に効果的です。ただし、地の文では「ら」を使った形にするようにしましょう。
「ら抜き言葉」になりやすい動詞のルール
ここからは少し専門的な話になりますが、「ら抜き言葉」がどのような動詞で起こりやすいのか、そのルールについて解説します。
日本語の動詞は、活用の仕方によっていくつかのグループに分けられます。「ら抜き言葉」が主に起こるのは、以下のグループの動詞です。
上一段活用動詞(かみいちだんかつようどうし)
辞書で引くときの形(終止形)が「~いる」や「~じる」など、「イ段の音+る」で終わる動詞です。例えば、「見る」「起きる」などです。
これらの動詞の可能形は、本来「見られる」「起きられる」となりますが、「ら」が抜けて「見れる」「起きれる」となりやすいです。
下一段活用動詞(しもいちだんかつようどうし)
終止形が「~える」や「~ぜる」など、「エ段の音+る」で終わる動詞です。例えば、「食べる」「寝る」などです。
これらの動詞の可能形も、本来「食べられる」「寝られる」となりますが、「ら」が抜けて「食べれる」「寝れる」となりやすいグループです。
カ行変格活用動詞(かぎょうへんかくかつようどうし)
現代の日本語では「来る(くる)」一語だけがこのグループです。
「来る」の可能形は、本来「来られる(こられる)」ですが、「ら」が抜けて「来れる(これる)」となりやすい動詞です。
一方で、次のような動詞のグループでは、通常「ら抜き」は起こりません。
五段活用動詞(ごだんかつようどうし)
「書く」「話す」「立つ」など、最も種類が多い動詞のグループです。これらの可能形は「書ける」「話せる」「立てる」のように、元々「ら」が入らない形になるため、「ら抜き」の対象にはなりません。
サ行変格活用動詞(さぎょうへんかくかつようどうし)
「する」一語(と、それを含む複合動詞)がこのグループです。「する」の可能形は「できる」という別の言葉を使うのが一般的なため、これも「ら抜き」の対象にはなりません。
このように、動詞のグループによって「ら抜き」が起こりやすいかどうかが決まっています。
まとめ
「ら抜き言葉」は、単に日本語の乱れとして片付けられるものではなく、言葉が持つ変化のダイナミズムや、コミュニケーションをより円滑に、よりシンプルにしようとする人々の工夫の一端を示す現象ともいえます。その背景には、多くの意味を持つ助動詞「られる」のわかりにくさを解消したいという合理的な側面や、言いやすさといった要因があると考えられます。
しかしながら、現時点では社会的に完全に市民権を得ているわけではなく、特に書き言葉やフォーマルな場面では、伝統的で規範的な形が依然として求められる傾向にあります。
言葉は常に変化し続けるものなので、今後、「ら抜き言葉」がさらに広く受け入れられ、将来的には誰もが自然に使う表現として定着する可能性もゼロではありません。その変化に目を向けつつも、現状の社会的な受容度や規範を理解し、相手や場面に応じた適切な言葉遣いを心がけることが、円滑なコミュニケーションを築く上で大切なことだと思います。