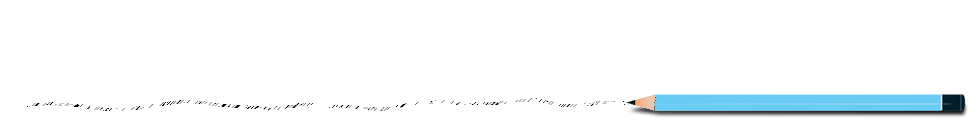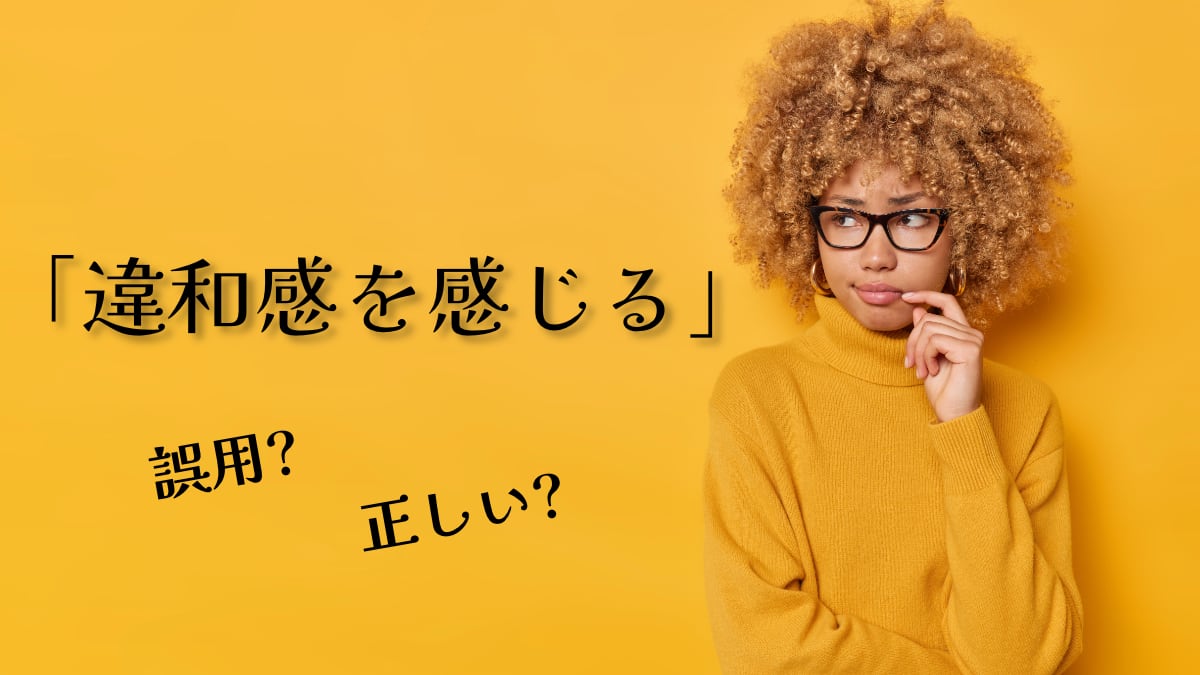「違和感を感じる」という日本語表現について「正しくない」「重言である」といった指摘を耳にすることがあります。日常生活やメディアでもしばしば見聞きするこの表現は、果たして本当に問題のあるものなのでしょうか。
結論からいうと、この表現は日本語の文章として間違いであると断定はできないと考えます。ただし、これは積極的に使用を推奨する、ということではありません。これについては「まとめ」の部分で解説します。
「違和感を覚える」という「正解」
まず「違和感を感じる」という表現が不適切であるならば、どのような言い換えが「正解」なのでしょうか。
これに関しては、一般的に「違和感を覚える」や「違和感がある」といった表現が適切であるとされています。これらの表現が日本語として自然かつ正確であるということについて、異論を唱える向きは少ないでしょう。
しかし、ここで一つの疑問が生じます。
「違和感を覚える」の「覚える」と「違和感を感じる」の「感じる」は、どちらも動詞であり、この文脈で用いられる際の意味合いも非常に近いものです。「対象となる物事を知覚し、心に受け止める」といった共通のニュアンスを持っています。そうであるならば、なぜ「覚える」を用いた表現は正しく「感じる」を用いた表現は間違っているとされるのでしょうか。
ちなみにこの部分が、私が最初に引っかかったところでもあります。同じような意味合いの動詞なのに、なぜ「覚える」はよくて「感じる」はだめなのかという疑問です。
「違和感を感じる」が問題視される理由
「違和感を感じる」という表現が「間違い」あるいは「不適切」とされる主な根拠は、それが「重言」(じゅうげん)だとされているからです。重言とは、同じ意味の言葉を不必要に重ねて使う表現のことを指します(二重表現、重複表現とも呼ばれます)。例えば「頭痛が痛い」(「頭痛」自体に「頭が痛い」の意味が含まれる)や「馬から落馬する」(「落馬」自体に「馬から落ちる」の意味が含まれる)などが典型的な重言の例として挙げられます。
このような表現は、冗長であり、文章をわかりにくくする可能性があるため、一般的には避けるべきとされています。実際に、言葉の規範に関わる公的な文書でも、この表現について言及している箇所があります。
文化庁の文化審議会国語分科会が2021年に発表した「新しい『公用文作成の要領』に向けて」の中の「紛らわしい言葉の扱い」の項目で「冗長さを避ける」ための具体例の一つとして「違和感を感じる」を挙げ「違和感を覚える、違和感がある」へと修正することが推奨されています。
Ⅱ-5 紛らわしい言葉の扱い
ウ 冗長さを避ける
(ア)表現の重複に留意する
意味が重複する表現(「重言」「重ね言葉」などとも。)は、むやみに用いないようにする。
例)諸先生方→諸先生、先生方 各都道府県ごとに→各都道府県で、都道府県ごとに
第1日目→第1日、1日目 約20名くらい→約20名、20名くらい
違和感を感じる→違和感を覚える、違和感がある出典: 文化審議会国語分科会「新しい『公用文作成の要領』に向けて」
国の機関が関わる文書でこのように例示されているのであれば「違和感を感じる」はやはり明確に避けるべき表現であり、議論の余地はないように思われるかもしれません。しかし、私はこの表現が、先に挙げた「頭痛が痛い」のような典型的な重言とは、性質が異なるのではないかと考えています。
「違和感を感じる」は重言にあたるのか
「違和感を感じる」が重言であるとされるのは「違和感」の「感」の字が「感じる」という意味を内包しているため「感」と「感じる」で意味が重複するという解釈に基づいています。しかし、言葉の構造をより詳しく見ていくと、異なる解釈も見えてきます。
「違和感」という言葉は、「違和」つまり「周囲の状況や本来あるべき姿とうまく調和せず、しっくりこない状態」が存在し、それに対して私たちが心に抱く特有の「感じ」や「気づき」を指す名詞として考えることができます。この場合の「感」は、動詞の「感じる」と同じものではなく、例えば「安心感」「幸福感」「罪悪感」といった言葉に見られるように、ある状態や性質から生まれる感覚や感情を示す名詞を作り出す、接尾辞的な役割を担っていると捉えることも可能です。
このような解釈を採るならば「違和感」は「ある種の感覚」を示す独立した名詞として扱うことができます。そして「感じる」という動詞は、多種多様な感覚や感情をその対象(目的語)とすることが可能になります。「寒さを感じる」「喜びを感じる」「痛みを感じる」といった言い回しが、文法的に全く自然であるのと同じように「違和感という種類の感覚を、感じる」という組み立て方も、論理的に破綻しているとはいえないのではないでしょうか。
つまり「違和感」という言葉自体に「感じる」という動作が完全に含まれているわけではなく、あくまで「違和」という状態から派生する特定の「感覚の種類」を示していると考えるならば「違和感を感じる」という表現は、必ずしも意味の完全な重複、すなわち典型的な重言とはいえない可能性があります。
それでも重複と感じる心理
意味構造の上では必ずしも重言とはいえない「違和感を感じる」が、それでもなお多くの人に重複表現であるという印象を与えるのはなぜでしょうか。その一因として、言葉の響きや見た目の印象が影響している可能性が考えられます。
「違和感」の末尾の「感(かん)」と、それに続く「感じる(かんじる)」という言葉は、音声的にも視覚的(漢字の「感」)にも完全に同一のものです。この音と形の連続的な一致が、意味的な重複とは別に、直感的に「同じことを繰り返している」という印象を与えやすいのではないでしょうか。人間が言葉を認識する際には、意味内容だけでなく、こうした音韻や形態も無意識のうちに影響を及ぼすことがあります。
したがって「違和感を感じる」に対する一部の否定的な反応は、厳密な意味論的分析というよりは、語感や言葉遣いに対する個人の価値観、あるいは簡潔さを求める規範意識から生じている側面もあるのかもしれません。
身も蓋もない言い方をすれば「『感』が続いて、なんか気持ち悪く感じる」ということです。
「〇〇感を感じる」~類似表現との比較
ここで、他の「〇〇感を感じる」という形式の表現に目を向けてみます。
私たちのまわりには「危機感を感じる」「嫌悪感を感じる」「罪悪感を感じる」「優越感を感じる」「劣等感を感じる」「満足感を感じる」「責任感を感じる」「背徳感を感じる」など、多くの類似表現が存在します。これらの表現は、日常的にも文章語としても広く使われており「重言である」として厳しく問題視されることは「違和感を感じる」ほど多くないように思われます。
これらの表現が許容されるのであれば「違和感を感じる」だけを特に厳格に排除しようとするのは、一貫性に欠けるという見方もできます。これらの「〇〇感」もまた、特定の状態や感情から生じる「感覚の種類」を示す名詞であり、それに「感じる」という動詞が接続している構造は「違和感を感じる」と共通しています。
「覚える」と「感じる」のニュアンス
さらに「違和感を覚える」という推奨される表現と「違和感を感じる」との間には、微妙なニュアンスの違いが存在していることも考慮すべきです。
一般的に「覚える」という言葉が示す感覚の発生は、比較的受動的、あるいは瞬間的に心に生じるものとして捉えられます。一方で「感じる」という言葉には、より能動的にその感覚を捉えようとする意志や、ある程度の持続性を伴ってその感覚を認識するといったニュアンスが含まれています。
もし、書き手や話し手が、こうした「感じる」特有のニュアンス――例えば、意識的にその違和の正体を探ろうとしている、あるいはその違和感が持続的に意識されているといった状態――を表現したいと意図した場合「違和感を覚える」では必ずしもその機微を汲み取りきれないかもしれません。
言葉の選択は、意味の正確性だけでなく、こうした細やかなニュアンスの表現にも関わってきます。
まとめ: 「違和感を感じる」を使うべきか否か
以上の考察を踏まえると「違和感を感じる」という表現は、単純に「間違いである」と断定することはできないことがわかります。言葉の構造を見ても、必ずしも典型的な重言とはいえず、類似表現の存在や「感じる」という動詞が持つニュアンスも考慮に入れると、この表現を一律に誤りとすることはできないのではないでしょうか。
もちろん、文化庁が示すように、公用文などにおいては簡潔さや明確さが特に重視されるため「違和感を覚える」や「違和感がある」といった、より誤解の少ない表現が推奨されることには合理性があります。また、言葉の響きや語感から「冗長だ」と感じる人がいることも事実でしょう。しかし、それはこの表現が日本語の構造として「絶対に間違っている」ことを意味するものではありません。最終的にどのような言葉を選ぶかは、文脈や相手、そして自分自身の表現意図によって判断されるべきです。
とはいえ「違和感を覚える」や「違和感がある」といった、よりスムーズに受け入れられやすい言い換え方があるのもまた事実。世の中には、言葉の使い方に敏感な、いわゆる「違和感警察」と呼ばれるような人々もいるわけで、そういった層から思わぬ指摘を受けないように、あえて使わないという選択もありだと思います。そこで争ったところで何かが得られるわけでもないですしね。