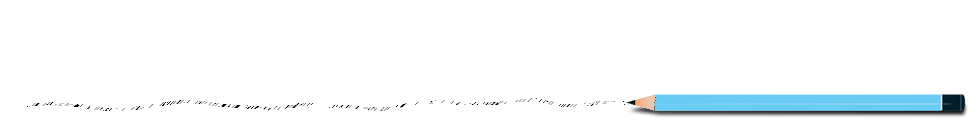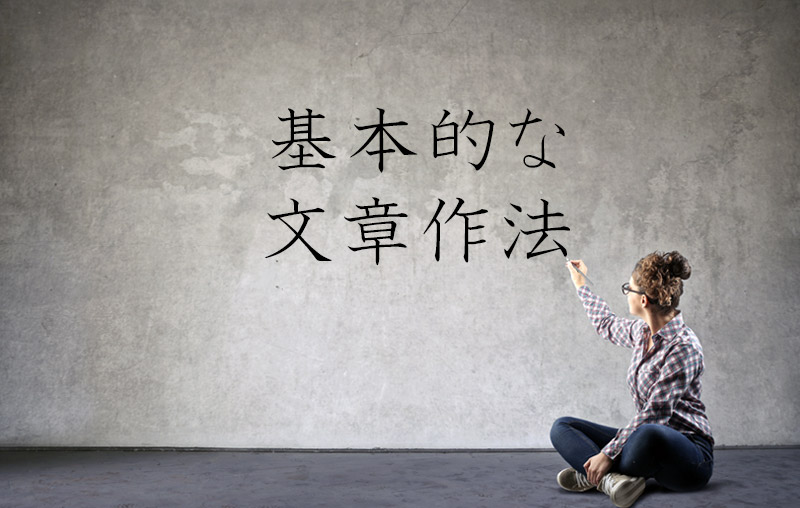ここでは文章作成の基本となるルールについて紹介します。読みやすく、意図が正確に伝わる文章を書くためには、いくつかの基本的な作法を理解しておくことが大切です。
段落と行の基本
文章の見た目や区切りを整えるためのルールです。
文の始めは一字下げる
書き出しや段落の始めでは、原則として最初の一文字分を空けます。ただし、会話文を鉤括弧(「」)で始める場合、その行頭の一字下げは不要です。
ちなみに、ウェブサイトの記事では、デザインの観点から一字下げを行わずに詰めて書かれることもあります。
改行のタイミング
段落(ひとまとまりの文章)が変わるときや、話の大きな区切りで改行します。読みやすさを考慮し、特にウェブ記事では、内容の区切りごとに適度な改行を入れると効果的です。
行末の処理(禁則処理)
句読点や閉じ括弧(」)が、行の先頭に来てしまわないようにするルールがあります。原稿用紙など手書きの場合は、前の行の最後のマスに一緒に入れる「ぶら下げ」という処理を行いますが、パソコンのワープロソフトやテキストエディタでは、多くの場合、自動的に行頭禁則・行末禁則の処理が行われるため、通常はあまり意識する必要はありません。
記号・約物の基本的な使い方
文章に区切りをつけたり、特定の意味合いを持たせたりする記号の使い方です。ちなみにこれらの記号を「約物(やくもの)」といいます。
句読点(「。」と「、」)
句点(。)は文の終わりに打ちます。読点(、)は、文の途中で意味の区切りを示したり、読みやすくしたりするために使います。主語の後や接続詞の後、言葉を並列する際などが読点を打つ目安ですが、打ちすぎても読みにくくなるためバランスが大切です。
疑問符(?)と感嘆符(!)
疑問符(?)や感嘆符(!)を使った後は、原則として一文字分のスペースを空けます。これらの記号の直後には、句点(。)や読点(、)は打ちません。
スペースの例外
行末に疑問符や感嘆符が来た場合、その記号でマスを終え、次の行は通常のルール(段落の始まりなら一字下げなど)に従います。記号の後のスペースは不要です。
会話文の終わりがこれらの記号で、その直後に閉じ鉤括弧(」)が来る場合は、記号と閉じ鉤括弧の間にスペースは入れません。
例:
◯「本当ですか?」
×「本当ですか? 」
括弧の使い分け
括弧にはさまざまな種類があり、用途に応じて使い分けます。
- 鉤括弧「」: 会話文、引用、特定の語句の強調などに使います。
- 二重鉤括弧『』: 書名、作品名、または鉤括弧の中でさらに会話や引用を示したい場合に使います。
- 丸括弧(): 補足説明、注釈、読み仮名などに使います。
三点リーダー(…)
文末や文中で、言葉の省略、無言、沈黙、余韻などを表すのに用います。通常、二つ(「……」)続けて使われることが多いですが、一文字分(「…」)で使われることもあります。
繰り返し符号(踊り字)
同じ漢字や仮名を繰り返す時に使って、表記を簡略化する記号です。「人々(ひとびと)」のように漢字を繰り返す「々」(同の字点、ノマ)や、「いすゞ」のように平仮名を繰り返す「ゝ」(一の字点)、「ゞ」(濁点付き一の字点)などがあります(片仮名の場合は「ヽ」「ヾ」)。
ただし、公的な文書やビジネス文書では、「ゝ」「ゞ」と「ヽ」「ヾ」は使わずに、仮名をそのまま表記することが一般的です(「いすゞ自動車」などの固有名詞は除く)。
引用の仕方
他の文章や言葉を引用する際は、短い場合は鉤括弧「」や二重鉤括弧『』(主に書名など)で囲みます。数行にわたるような長い引用の場合は、改行し、引用部分全体を本文より二文字分下げて記述します。
文字表記のポイント
数字やアルファベット、漢字と平仮名の使い分けなど、文字表記に関する基本的なルールです。
数字の表記
横書きではアラビア数字(1, 2, 3…)を、縦書きでは漢数字(一, 二, 三…)を用いるのが一般的です。
アルファベット・カタカナの表記
外来語はカタカナで表記します。アルファベットを用いる場合は、大文字・小文字の使い分けや、全角・半角の統一も意識すると読みやすくなります(ウェブでは半角が好まれる傾向にあります)。
漢字と平仮名のバランス
常用漢字を目安に漢字を使用し、平仮名とのバランスを考えることが大切です。あえて平仮名で書く「開く」表現(例: 「事」→「こと」、「物」→「もの」など)と、漢字で書く「閉じる」表現を文脈に応じて使い分けることで、文章の印象や読みやすさが変わります。
送り仮名のルール
漢字に続く送りがなは、内閣告示の「送り仮名の付け方」に基づいたルールがあります。一般的な慣例に従うことで、誤読を防ぎ、読みやすい文章になります。
→ 文化庁「送り仮名の付け方」(外部サイト)
文の構成と表現
文全体の組み立てや、表現方法に関する基本的な注意点です。
主語と述語の対応
一文の中で、主語(誰が、何が)と述語(どうする、どんなだ)が正しく対応しているかを確認しましょう。文が長くなると、主語と述語の関係が曖昧になりやすいので注意が必要です。
修飾語と被修飾語の関係
修飾語がどの言葉を説明しているのか(被修飾語)を明確にすることが大切です。修飾語と被修飾語が離れすぎたり、複数の解釈ができるような曖昧な位置にあったりすると、誤解を招く原因になります。
敬体(です・ます調)と常体(だ・である調)の統一
一つの文章や記事の中で、文末の表現(~です・ます/~だ・である)は、どちらかに統一するのが基本です。混在していると、読者にまとまりのない印象を与えてしまいます。
注意したい表現
読みやすさや正確さの観点から、使い方に注意したい表現があります。
- 体言止め: 文末を名詞で終える表現。効果的に使うと余韻を残せますが、多用すると稚拙な印象や、文章が途切れているような印象を与えることがあります。
- ら抜き言葉・い抜き言葉: 「見られる→見れる」「書いている→書いてる」など、言葉の簡略化として広まっていますが、公的な文書やビジネス文書では避けるのが一般的です。
- 擬音語: 文章に生き生きとした表現を与えますが、多用しすぎると逆に内容が伝わりにくくなったり、文体が軽くなりすぎることがあります。
まとめ
文章作成の基本的な作法は、情報を正確に、そしてわかりやすく伝えるための土台となります。今回紹介したルールを意識するだけでも、文章の質は大きく向上するはずです。
それぞれのルールには、さらに詳しい内容や例外もあります。ぜひ、リンク先の個別の解説も参考にしてみてください。