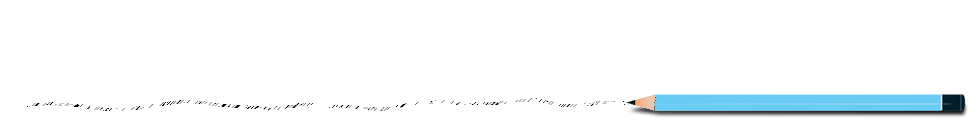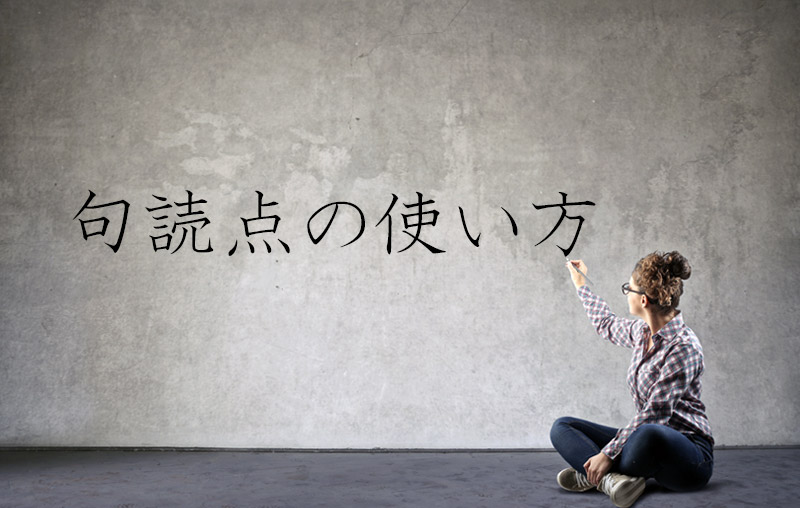句読点(くとうてん)は、ひとまとまりの文の途中に区切りとして打たれる読点(、)と、文の終わりに打たれる句点(。)をまとめた呼称です。その使い方について解説します。
ちなみに句点に関しては、会話文の鉤括弧の最後に打つか打たないかという問題があります。これについては鉤括弧の項で解説しているので、そちらをご覧ください。
句読点をどこに打つか
読点をどこに打つかというのは厳密には決まっていません。一般的には主語や副詞の後に打たれることが多いのですが、必ずそうしなければいけないというわけではないです。ここが難しいところで、決まっていないがゆえに、その人のセンスが問われるところでもあります。
読点を使わなすぎると文の意味がつかみづらくなるので避けるべきですが、逆にあまり多く使いすぎても読みにくくなりますし、文章を散漫に感じさせてしまう恐れがあるので注意が必要です。文意を損なわないのを前提に、リズムよく読めるような位置に打つようにしましょう。
読点を打つ位置については、好きな小説を参考にするのもいいと思います(翻訳ものの場合は翻訳者のセンスになってしまいますが)。
読点を打つ場所で文の意味が変わる場合がある
上で述べた“文意を損なわない”という点についてですが、読点を打つ位置によって意味がまったく異なってしまう文章があるので気をつけましょう。
上記の文は、私が泣いているのか彼が泣いているのかはっきりしません。これを読点で区切ると文意が明確になります。
私は泣きながら、走る彼を見つめていた。
また、主語や目的語の位置を変えることで、読点を使わずに表現することもできます。
私は走る彼を泣きながら見つめていた。
横書きにおける読点とコンマ(カンマ)
教科書や公文書で横書き表記するときは、読点ではなくコンマ(,)を使うことになっています(この場合、文の終わりはピリオドではなく句点を使うのですが、理系の論文では句点ではなくピリオドを使うのが慣例化しています)。
もっとも現在の出版物やインターネット上のメディアの記事においては、横書きでもそのほとんどが読点を使っています。公文書や論文以外では読点を使っても問題ないといえるでしょう。
原稿用紙での句読点の使い方
原稿用紙では、一字分を使って句読点を打ちます。ただし句読点が行の最初に来る場合は、前の行の最後のマスに文字とともに入れます。
句点のあとに一字分あける必要はありません。
出版社のルール
余談ですが、かつてとある分野の解説書を執筆した時に、下書きを編集の人に送ったのですが、大量の読点が付いて返ってきたことがありました。当時私は読点をあまり付けないほうが文体としてスタイリッシュだと思っていたので、「読点を少なくするのってだめですかね」と編集の人におずおずと聞いてみたのですが、出版社内の校正ルールがあるとのことで断られてしまいました。
まあ小説などの自分の創作物ならいざ知らず、頼まれて書いた専門書で我を通すメリットはないので、「なるほど〜」と言ってそのままお任せしたわけですが。